構造設計のはじめは二次部材の検討から入ることも多いと思います。
二次部材と呼ばれていますが、当然軽視してよいものでもないし、簡単に設計できるものではありません。
そんな二次部材を設計する際に留意することについて書いていきたいと思います。
①二次部材とは
二次部材については明確な適宜はありませんが、主には建築構造において柱や梁といった長期荷重や耐震要素として直接的に地震力を負担している以外の部材を二次部材と言っています。
二次部材を経由して、柱や大梁や耐震壁や耐震ブレースに力を流している役目とも言えます。
どんなに柱や大梁を精度よく設計したとしても、そこまでに力を流すための二次部部材の設計が不十分であっては役割を果たせません。
二次部材は具体的には、スラブ、小梁、間柱、胴縁などが該当します。
これらの部材は柱や大梁と比べて、局所的に大きな荷重が作用する可能性が高いので、積載荷重、風荷重などの荷重設定が非常に重要になります。
耐震設計手法のように建築基準法で細かに規定されてはいません。それだからと言うわけではありませんが、長期的、短期的にどのような大きさ、方向から力が掛かるのかを想定して検討する必要があります。ここが二次部材設計の面白い所でもあります。
二次部材は繰り返しで同じものが配置されることが多いので初期のルール設定も重要になってきます。考え方がわかりやすいルール作りを意識しましょう。
部材符号の設定の仕方に設計者の力量が見えます。ざっくり言うと符号がやたら多いと場当たり的な思考に見えてしまいます。
該当範囲が広いので施工の容易さや経済性への影響も大きくなります。
時間軸も含めてあらゆる角度から整理・検討するようにしましょう。
②計算の仮定と実態を繋げる
二次部材は不静定次数が低いこともあって計算方法が単純ではありますが、その分、安全率が低いとも言えるので、その計算の中で仮定している条件と現実が違っていると影響が露骨に現れることになります。
そのため、計算で想定している力の流れ方や、接合部の固定度の評価が現実のディテールと整合していることが重要になります。具体的にどの鉄筋やボルトなどが引張力やせん断力がどこを通って力が流れたり、回転を拘束しているのかを一致させながら断面を考えます。
計算条件では固定としていても、実際には曲げに対しての反力が取れる部材がなかったり、逆にピン支持で仮定していたのに、回転を拘束するような接合部になっているということがないようにしましょう。
構造設計の中では力の総量(荷重)が減っていない限りは、どこかで応力が小さくなっていれば、代わりにどこかの応力が大きくなっています。なので、どこかの応力が小さくなっていれば代わりにどこの応力が大きくなっているのかまでセットで確認するようにしましょう。
計算を満足させるために安易に条件を変更するのではなく、本質的な部分で調整をするようにしましょう。
参考:力の流れの作り方
③トラブルになりやすいのも二次部材
トラブルにつながりやすいものも実は二次部材です。
それは繰り返しになりますが、単純なだけにその分、安全率が低いとも言えるので、予想外の力が生じると耐えられない確立が高いです。
まず最も影響が出やすいのは変形による影響です。床、壁共に仕上げ材のひび割れや建物の使用感に悪影響を与える可能性があります。
設計を始めたばかりの時には許容応力度設計に夢中になりすぎて変形に対しての意識が薄くなりがちですが、変形はトラブルに直結しやすいこともあり、使用上支障が生じないようにと、変形については告示にも記載があるくらいです。
固定端とピン接合では応力も変形も倍半分で変わってきます。計算書としては1つの条件で検討しないといけないわけではないので、考えられるいくつかの条件を検証して、適切は判断をしていきましょう。
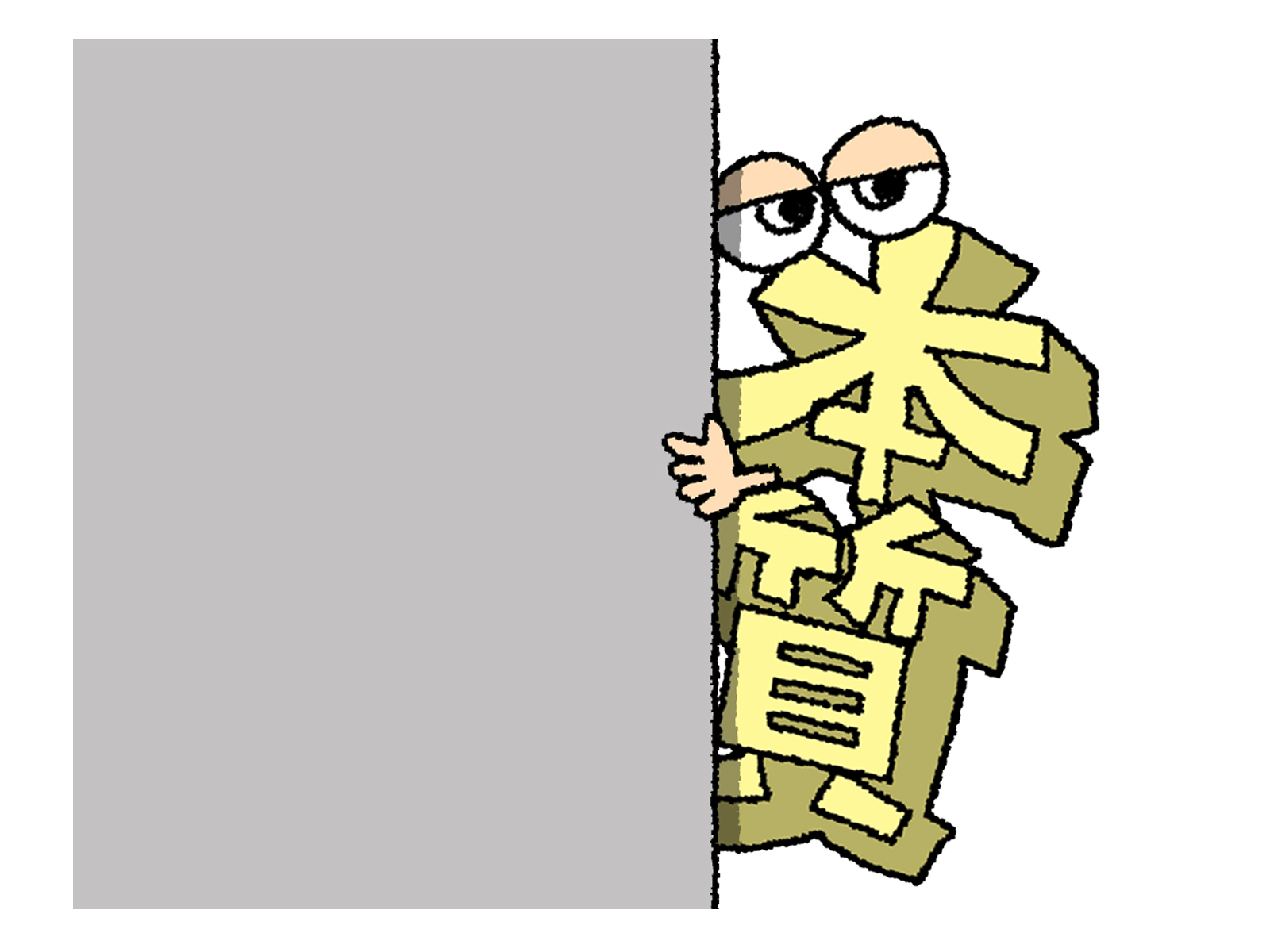

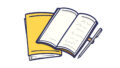
コメント