応力図は構造設計をする上では、読むことも書けることも必須の能力になってきます。
基本的なことなのですが、最近は電算に基本条件を入力すると自動で作成してくれて、その数値を使って、断面算定までしてくれます。そのため前段の準備計算や応力図を飛ばして、入力条件や断面算定の結果ばかりに注目しがちです。
そもそも応力図が違っていたら断面算定も意味がないし、応力図の数値を見ることで数値感や力の流れが把握できるようになっていきます。
構造設計一級建築士の試験でも応力図をチェックする法適合問題も出ることがあります。
今回は応力図のチェックの視点について書いていきたいと思います。チェックの手順は応力図を書く時の手順とは少し異なる順番にしています。その理由も後に記載します。
剛域などの準備計算を含めた内容は別の記事で書いていくので今回は基本的な部分に絞って書いていきます。
3つの手順として示していきます
①変形と反力
②曲げモーメント図の形状
③軸力・せん断力の量
①変形と反力
チェックの手順としては手計算などの自分が確実に把握できるかつ間違っていればすぐに気づけるものから順に確認していくことで効率的かつ精度のよいチェックができます。
変形量については正確に算出するのは複雑になりますが、変形の形であれば力の向きがわかっていれば想定ができます。違っていれば荷重の入力の向きや、支点の配置を間違えている可能性があります。
支点と密接な反力についても想像がしやすい内容です。力を流して受け止められる(ある方向の変形がゼロになる)箇所を支点としてます。例えば、地面に接している箇所などです。
支点にきちんと反力が生じていること、意図した方向に対しては変位がゼロになっていること、(ピン支点であれば鉛直と水平の変位がゼロ、ローラー支点であれば鉛直の変位はゼロだけど、水平方向は変位が生じる。)、支点の反力の合計が、入力荷重の合計と同じであることが確認することになります。
支点の反力の合計が想定した数値(入力したと思っている数値)と違っていれば、荷重の入力で間違えている可能性があります。(荷重の向きを示すプラスマイナスの定義の勘違い、等分布荷重の負担幅の認識違い、単純な数値の入力間違えなど)
※細かい補足ですが、部材に対しては変形(形状や寸法が変わる)、支点については変位(位置が変わる)と言います。
②曲げモーメント図の形状
曲げモーメントのポイントはモーメント図の向きと支点、接合部の条件との整合、総体関係です。
変形と近い関係になる曲げモーメント図の形状を確認します。曲げモーメント図の基本になりますが、部材が変形することで引張力を負担している側に対してモーメント図の線が出てくるように書きます。
なので、部材の変形を見ればどちら側が引張力がかかっているかが想定できます。(梁が鉛直荷重を受けている場合には中央の梁の下が引張られる=伸びる)
向きの確認と、接点での曲げモーメントの値の合計がゼロになっていること、ピン支持やピン接合部分ではゼロになっていること、逆に固定や半固定の回転剛性がある部分には曲げモーメントが発生していることを確認します。
剛床過程についての詳細については今後書きますが、接点での曲げモーメントの値の合計がゼロになっている場合でも、例えば柱の大梁の取りついていない箇所で曲げモーメントの向きが急に変わっていたらそれは、本来は非剛床にするべき箇所が剛床になっているという間違えの可能性があります。
あとは接点部分での曲げモーメントの分担比率です。基本的な剛性が高い部材の方が発生する曲げモーメントは大きくなるので、部材せいが大きい、部材が短い側の曲げモーメントが大きくなります。
③軸力・せん断力の量と向き
変形と反力、曲げモーメント図形状といった直感に近い部分でチェックできるものから順に確認して最終的には電卓レベルで確認できる数値を確認していきます。
ここでも詳細な数値を合わせるというよりも、趣旨を踏まえてオーダーがあっていることを把握することが大事になります。
応力図を書く際にはせん断力を先に決めてモーメント図にしていきますが、チェックの場合には詳細な数値を確認する前に間違えに気づいた方が効率よく業務が進められることから順番を逆にしています。
柱の軸力については柱が負担している面積、大梁のせん断力については大梁が負担している面積を概算すれば簡単にオーダーに狂いがないかを確認できます。
モデルによっては長期荷重時に柱に圧縮力ではなく引張力が発生することがあるので、意図して引張材として考えていなければ何かモデル化が間違えている可能性もあります。(この見落としは確認申請の指摘などでも割とよくあります)
地震時の水平力の負担は、水平剛性の高い所が多く負担しているかといった比の概念を持って確認するようにしましょう。総体量については支点反力段階で確認しておきましょう。
水平力を負担した場合には、柱に引張力が掛かるものと、圧縮力が掛かるものがあるのでその分類が間違っていないかは変形図と関係づけて確認するようにしましょう。基本的には荷重の方向に対して前側に圧縮力、後ろ側(浮き上がる側)に引張力が発生します。
応力図のチェックができるようになれば力の流れのコントロールに近づいていきます。
【構造設計】力の流れとは?力の流れをコントロールしよう!
この記事の続きになります⇒【構造設計】曲げモーメント図の向きが重要な理由
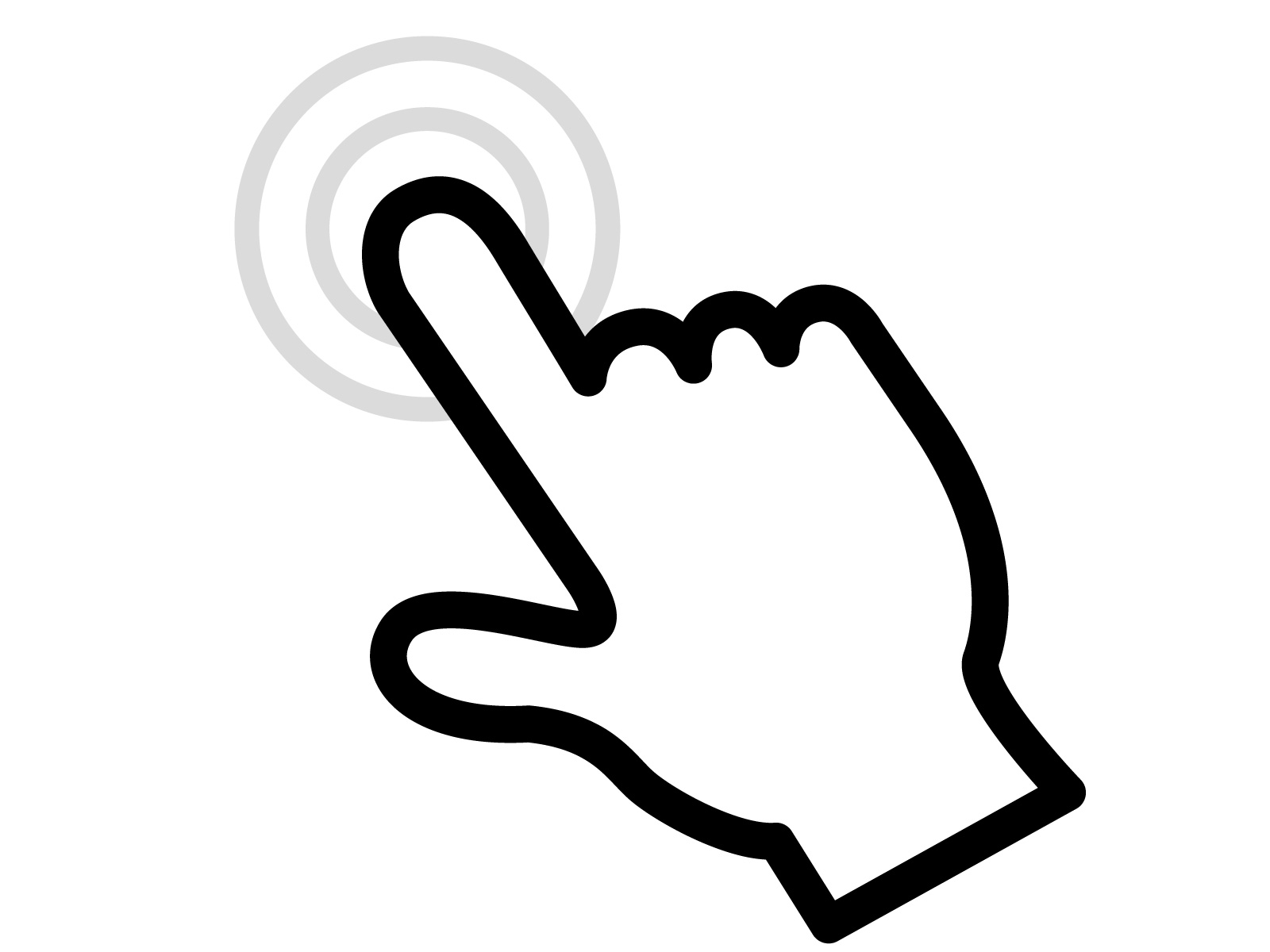


コメント