構造設計の中での大地震に対する検討の考え方について以下の記事で書いてきました。
大地震時には損傷前提で設計している!?
今回はそれらも踏まえて具体的な検討法の留意点について書いていきたいと思います。
①地震に対してどんな検討をしている?
構造設計の中で地震に対する検討方法は大きく分けて静的解析と動的解析の2つの方法があります。
地震が発生すると当たり前ですが建物は揺れ動きます。その揺れ動いたことによって建物に掛かる力を一定の方向性を持った力として建物に負荷するものは静的解析、実際に地震の波を想定して、建物の計算モデルを地震が生じたときのように動かしてみることを動的解析と言います。
簡単な解説を聞いただけでも、静的な解析に比べて動的な解析をするには時間もお金も掛かりそう、技術的にも高度という印象を受けると思います。
建築基準法上では、建物の高さが60mを超える場合や免震構造にするなど特別な場合を除いては静的な解析での計算を行えばよいことになっています。
※正確には免震構造でも告示免震といういくつかの条件を見たいしている場合には動的解析は不要になります。
そのため構造設計者は、多くの場合は静的解析のみを行っていますが、設計者によってはどんな建物に対しても動的解析をしてみて、建物の特徴を掴んでみるということをしている設計者の方もいらっしゃいます。
なぜこういった法体系になっているかの補足はこちらを参照してください。
⇒構造設計ルートの背景~法適合と耐震性能はイコールではない~
②エネルギーを消費して地震に耐えている
構造設計では地震により建物に入ってくるエネルギーを力に置換して解析を行っています。
理科や物理の授業で習った位置エネルギーや運動エネルギーを思い出すとイメージしやすいと思いますが、地震によって生じる力も加速度と重量を定量化して地震力という力に置き換えています。
なので建物が重いと地震力が大きくなり対抗するための耐震要素が多く必要になります。
揺れることでエネルギーを消費して建物の揺れは収まります。中地震であれば揺れだけでエネルギーを消費できますが、大地震のようにエネルギーが大きくなると揺れるだけではエネルギーを消費することができないので、どこかを損傷させることでエネルギーを消費します。なので、大地震時には損傷することが前提になります。
⇒大地震時には損傷前提で設計している!?
免震構造や制振構造というのは簡単にいうとエネルギーを吸収する部分をあえて作ることで、柱や梁といった部材を損傷させない構造形式です。
③地震に対してどう対抗するか?
地震による揺れのエネルギーは、慣性力(建物の重量が重く、加速度が大きい程大きくなる)によるもので、そのエネルギーに対抗する方式としては大きく二つに分けられます。
専門的な言葉でいうと強度型と靭性型に分けられます。簡単に言うと、硬いか柔らかいかになります。
硬い(剛性と耐力が高い)ものは、すこし揺らす(変形させる)のに大きなエネルギーが必要になります。一方で柔らかい(剛性が低い)ものは、大きく変形することでエネルギーを消費させます。
このように建物自体の剛性と耐力を高めて受け止めるか、剛性を小さくして変形することでエネルギーを受け流して(減衰を大きくして)建物自体の耐力は小さくするといった対極的な2つの特徴がありまる。これはどちらが良いかというものではなく、建物形態の特徴や使用する材料の特徴などによって最適なものを選択します。
また、この2つの特徴についても、両極端なものだけでなく適度なバランスを考えて両方の特徴を取り入れて設計していくことになります。
④保有水平耐力計算はあくまでも耐力の検討
建築基準法上の構造設計ルートのルート3いわゆる保有水平耐力計算(令第82条)は、名前の通り建物の保有している耐力に照準をあてた検討方法になります。
その建物のエネルギー吸収能力がどの程度あるのかを評価して、その吸収能力に応じてどの程度の耐力が必要になるのかを算出します。それを必要保有水平耐力と呼んでおり、その必要な耐力より建物が保有している耐力が高ければ、法的には耐震性を満たした建物ということになります。
ルート3の検討は一般的な確認申請の中では最も詳細な検討ルートになりますが、それを満足しているからといって安心してはいけません。
この保有水平耐力の検討は繰り返しになりますが、耐力に照準をあてた検討になるので、建物の変形量について評価できる検討方法になっていません。
⑤耐震性には耐力と剛性のバランスが大事
実際の地震の際の被害の大きさ、建物の継続的な利用という観点から言うと、建築物の構造体の耐力が高くても十分に安全と言えないことがわかってきています。
もう一つ重要なことは建物がどの程度変形したかということです。建物の中には構造躯体だけでなく、壁や天井や設備機器・配管などがあるのでそれが変形に追随できる程度に構造体の変形をおさえてておく必要があります。
想定以上に大きく変形してしまうと、壁や天井や設備機器・配管などが脱落や損傷をしてしまい継続使用を困難にしてしまうだけでなく、人命に関わる可能性があります。
建築基準法の中では大地震時の変形について明確な数値での規定は特にありませんが、近年では国土交通省の構造設計基準では変形に関する検討について、法とは関係なく行う方向に向かっています。
法で包括している範囲とそうでない範囲を理解した上で、設計者として適切に補完していくことが重要になります。
※建築耐震設計における保有耐力と変形性能(日本建築学会)は必読書だと思うのですが中古しかないようです。1990年版も存在します。ちなみに手元にあるのは1990年版です。
⑥詳細な検討をしたからと言って安全とは限らない
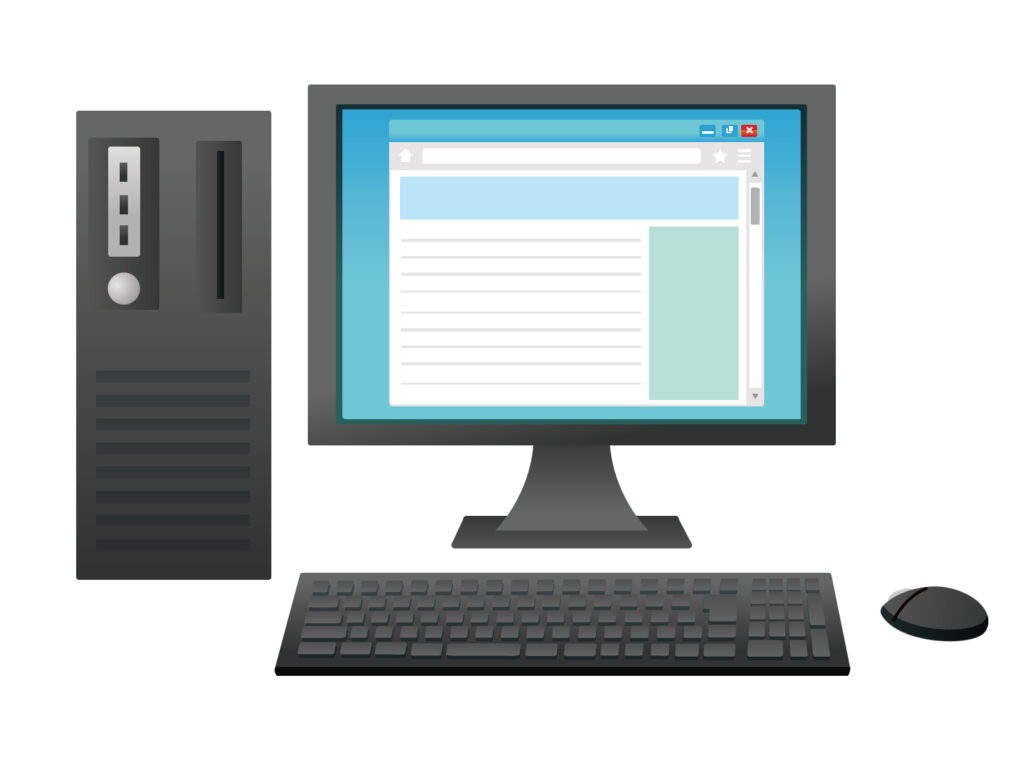
静的解析に比べて動的解析の方が高度な検討と書きましたが、だからと言って動的解析を検討法に沿って計算をしたからと言って安全だと考えてはいけません。
同じように静的解析な中でもルート1~3があって、規模が大きかったり複雑な建物になるにつれてルート3といった詳細な検討を行うことになりますが、ルート3の保有水平耐力計算を満足しているから安全だとは言えません。
構造計算はどんなハイテクなものを使って、詳細な検討を行ったとしても複雑かつ未知な自然現象の前では仮説でしかありません。このことは絶対に忘れてはいけません。
ましてや計算プログラムがOKという結果を出していたとしても、それに至るまでの条件の設定が誤っている可能性もあります。
それに気づくためにも常に、これまでの地震被害や逆に被害が少なかった建物と照らし合わせてみたりして、少し矛盾しているような言い方になりますが想定外なことが起こることを想定する必要があります。
構造計算の中で使う式には大きく分けて実験式と理論式の二つがあります。どちらなのかを踏まえて、どういった条件で導かれたもので、下限値なのか平均値なのかを理解して安全率をどの程度に設定するのかを考えることは重要なことです。
計算プログラムの結果を色々な角度で見てみたり、計算以外の根拠を考えて見たりと常に多面的な視点で検証することを忘れないようにしましょう。
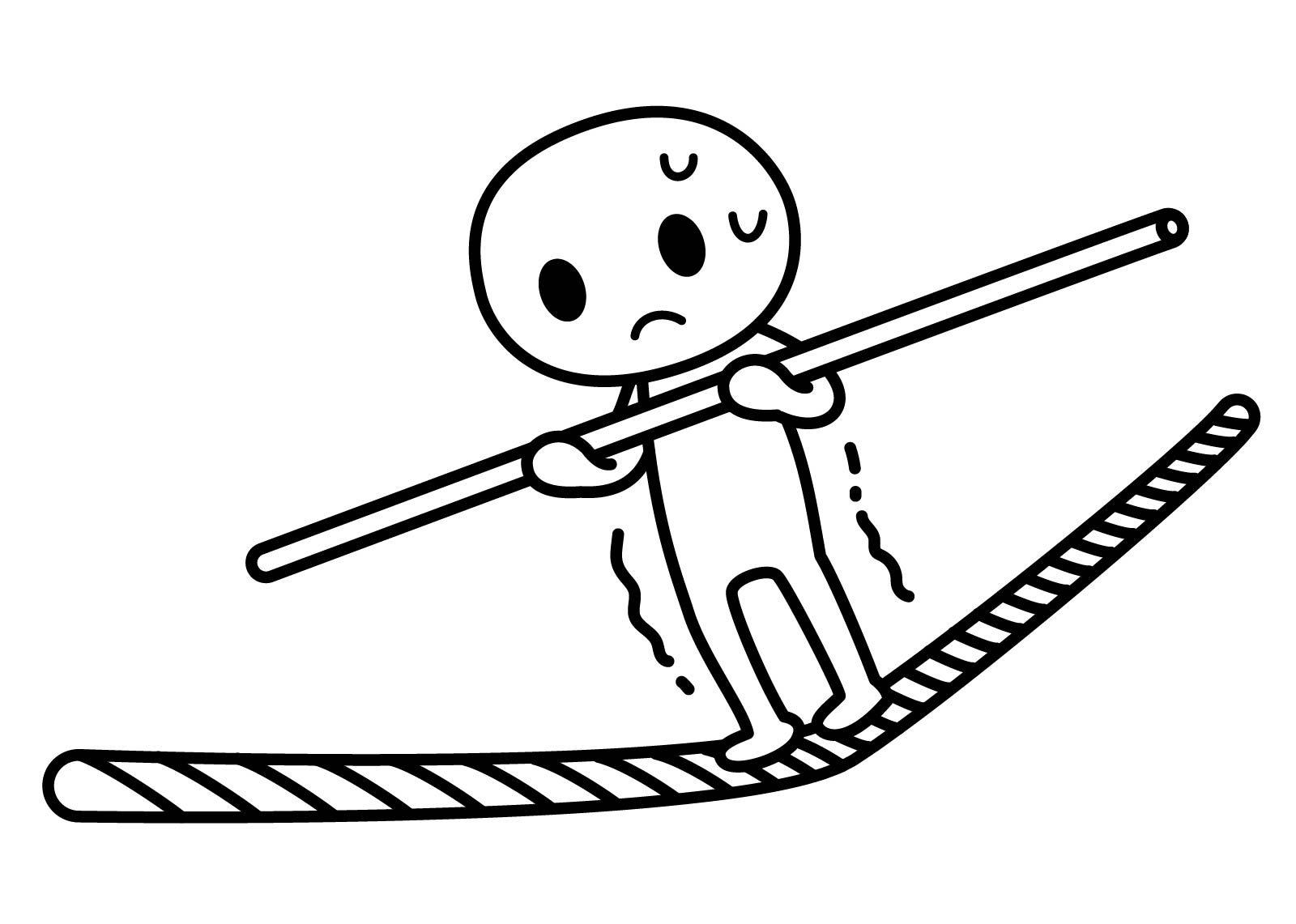


コメント