どんな仕事をしても必ず調べるということに時間を費やすことになります。
建築構造設計をしていてもたくさんの法的な基準や学会の指針、他社の作品の事例など情報がたくさんあります。
これらすべてを暗記できるわけではないので、大体どこにどんなことが書いてあるのかだけを覚えて、改めて使用するときに内容を確認するといった使い方をします。
少し話は反れますが、暗記することをやめるという意識は結構重要です。試験をするわけではないので素早く概要や世界観だけ理解して次に移るというスピード感がないと仕事の中ではついていけなくなります。
社会人では不可欠な調べものが上手くできれば確実に成果度も上がるようになります。
今回は調べものを上手くするためのポイントを書いていきたいと思います。
今回のポイントは3つになります
①仮説を持って調べる
②周辺知識も知っていく
③自分で答えが出せる充足感が得られる
①仮説を持って調べる
社会人になってからの調べものでは試験勉強の時のように知りたいことがそのまま書いてあることばかりではありません。しかも、教科書のように範囲を限定してくれているわけではないので、大量の情報の中から探すことになります。
そこで仮説を組み立てたり、照準力が必要になります。それを意識していない大量の情報に溺れてしまって、時間が経った割には何がわかったんだろう?ということもよくあります。
課題を進めることが上手い人というのは、未明課題に遭遇してもある程度の仮設を立ててすぐに調べることができる人です。
言われれば当たり前のことではあるので、仮説を持ってそれを検証する意識で情報を調べていくということを繰り返していけば割りと簡単に身に付くのですが、逆にやらないことにはいつまで経っても身に付かないで、差が付きやすいポイントでもあります。
②周辺知識も知っていく
考えて答えを出すにしても思考の基点となる参考は必要になります。
社会の中でまったく新しいものというのはほとんどありません。大抵が既知のものの組み合わせか応用でしかありません。なのでそれを知らずに参考もなく考えていても時間ばかりが掛かってしまいます。
考えることに力点をおきたくなりますが、考えることに力を入れるべきタイミングはある程度情報が揃ってからになります。
調べることが習慣になってくると、他の課題で気になっていたことのヒントになるものを見つけるなど、知りたいと思っていたこと以上の成果が得られるようになってきます。
そうなれば、全体的に答えを出すスピードも成長のスピードも速くなっていきます。
③自分で答えが出せる充足感が得られる
調べものをできる力・習慣を身に付ければ、手が止まるということもほとんどなくなります。
人に確認しないと進まないことはかなり限定的な内容になるはずです。
書物や事例で確認して得た知識というのは必ず対外的に使える武器になります。正直言って、聞いただけの話では根拠が弱くて対外的に使えません。
また、設計職のように専門的な技術的内容は、一度は書き言葉(出典元)で固定しないといつまで経っても、理解が浅く、論理整合性が自分の中でも取れないことになります。それでは当然相手に伝わるような説明ができないし応用は利きません。
何事においても中々一度で覚えることは難しいので何度か振り返ることになりますが、人に何度も同じことを聞くことはできませんが、書いてあることは何度でも反復できます。
始めのうちは聞いてしまった方が答えも早いし、わからなければ丁寧に解説もしてくれるので、調べることが億劫になってしまうかもしれませんが、慣れさえすれば自分で答えが出せる感覚やスピードが上がっている感覚もあるので新しい課題に直面しても答えが出せる自信がついていきます。
最後に人材育成での観点になりますが、答えや考え方を教えるのではなく調べ方を伝えてあげることが独り立ちさせるためには重要なことになります。
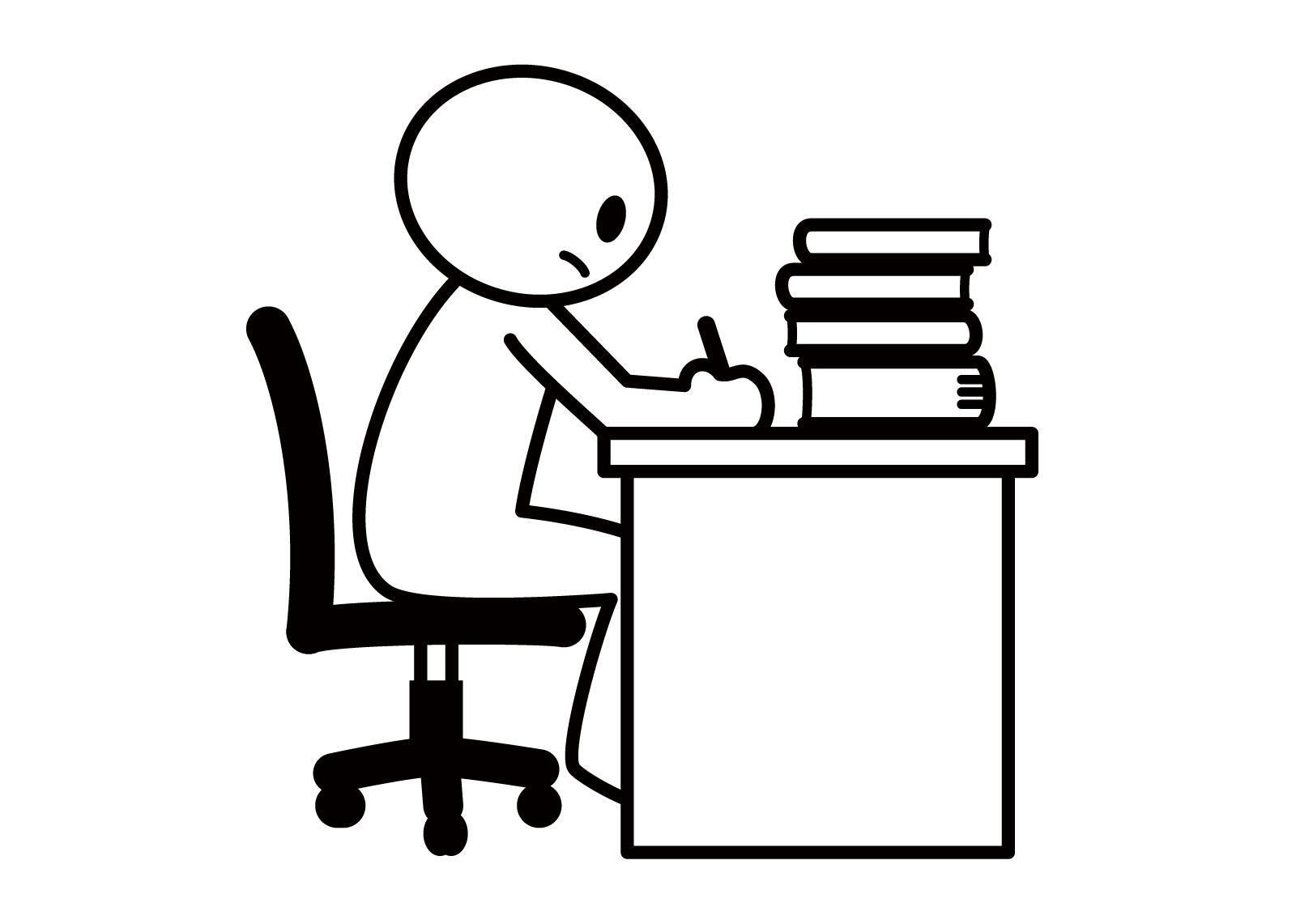


コメント