仕事を始めたばかりは知らないことばかりなので、誰かに何かを言われたときに多少の違和感があったとしても、それが正しいと思ってしまうことがあります。
また、段取り能力も不十分な中ですぐに課題を済ませたい気持ちが勝ってしまって、調べることを怠ってしまうこともしばしばあります。しかし、遠回りした方が結果的には最短の道になるということをおさえておきましょう。
今回は根拠をおさえることの重要性とそのおさえ方について書いていきます。
①知らないからこそ鵜呑みにしない
肩書きや立場だけでは、その人が正しいことを言っている根拠になりません。特に文章にせずに話し言葉ばかりの人は要注意です。自分でも明確に理解できていないから言葉にできていない可能性大です。そういった人は社会的には信用が得られません。
逆にきちんと根拠として法規や基準書のどこになんて書いてあると言った根拠をきちんと示せる人は信頼されるし、根拠を持って進めているので手戻りもないので仕事全般が早いです。
ネットなどで根拠不明の記述は根拠になりませんが、一次情報をネットで調べるのは早いので、どんどん使ってよいですが、最終的には前述したように法規や基準書と照らし合わせましょう。まずは、対外的な方にも示せるかを体感的な目安にしていくとよいと思います。1年目にこれを習慣化できれば未来は明るいです。
②正確に読み解く能力を身に着ける
自分で調べるようになった次にぶつかる壁が、正確に情報を掴めないというものです。そうなる原因の1つが都合のよい解釈をするということです。想定通りや時間を掛けずに課題を進めたいという意識の問題もあると思いますが、複雑な内容を読み解けるようになるには普段から気を付けるべきことがあります。
それは正しい言葉の定義を把握しようとすることです。建築設計の仕事の中で建築基準法といった法規や、建築学会の基準と言った文字が多く簡単には読み解けないものがあります。
こういったものを読み解くために必要なことは正確な言葉の定義をおさえることです。法や基準書というのは最初は馴染みにくい言葉も多くあるかもしれませんが、その分、言葉遣いの正しさは徹底してあります。一度定義された言葉が途中からちょっとニュアンスが変わっているなんてことはありません。
それだからこそ読み手側もなんとなくで解釈するのではなく、一度自分でも書き出してみるくらいに、正確に定義をおさえて言葉を使っていくと、あるとき驚くくらいに内容がすっと頭に入ってくる時がきます!
③根拠の積み重ねが結果に繋がる
建築の構造計算やエンジニアリングは文章が苦手でも計算が得意であることが重要と思うかもしれませんがそうではありません。
工学全般に言えることですが非常に複雑な自然現象を数量的に捉えるために、簡略化しているのが計算の世界です。色々な事象を類型化して少ない言葉や条件で捉えられるように定義(言葉化)してくれているので、定義をおさえることから計算の理解が始まると言えます。
計算の結果についてやり取りするなかでも、強い(剛性と耐力の概念がごちゃごちゃ)や壊れる(曲げ破壊?せん断破壊?許容応力度が満足していないこと?)といったなんとでもとれる幅のある言葉で答えることが多い人材は理解が進むのが遅いです。
言葉を正確な定義をおさえながら言葉を選んでいくだけで自分で考えられる幅が大きく変わってきます。
構造計算をする上でも、建築基準法、施行令、告示といった法的拘束性があるもから、建築学会関連の基準といった基本的には守るが法的拘束性のないものと、色々なヒエラルキーがあるので、大きな体系を理解しないでやみくもに適合させようとすると、設計で実現したいものから遠ざかり、設計者ではなく計算屋になってしまいます。
そうならないためにも根拠をしっかりとおさえられるようになりましょう。
参考:協議の心得
④暗記ではなく立ち戻れる仕組みを作る
構造設計に限った話しではないですが、建築設計はとにかく情報が多いです。設計チームとの調整情報、客先与件、各種基準等・・・
すべてを暗記することは当然不可能です。しかも建築プロジェクトは設計~竣工でも期間が長いですが、場合によっては使い始めてから振り返ることがあります。
なのでどこに何があるのかを把握して、立ち戻れるようにすることが大切です。この割り切りは非常に重要です。割り切ることでやり方が大きく変わります。
各種基準や法規に関して言えば、暗記をするのではなく、どこにどんなことが書いてあったかまで把握しておけば都度確認すれば問題なく業務を進められます。色々な業務の中で、自分のアンテナが反応できる程度に認識しておけば、調べに行けるのでまずはそれで十分です。
日々状況が変化していく、設計チームとの調整事項や客先打合せ事項については、自分で立ち戻れる仕組みを形成して習慣化することを早いうちから身に着けた人材は成果を出せるようになるのは早いです。
最近であればどこでも更新ができるグーグルのスプレッドシートなどを活用してすぐにデータ化していけば良いと思います。議事録については打合せと一連の流れで時間を取っておくことで、思い出すという無駄な時間が発生しないので確実に仕事は早くなります。
自分だけでなく周囲との課題意識もすぐに揃えることができるので、周囲の仕事の効率も上がります。
⑤学びなおしのススメ
暗記をしようと思わなくても、繰り返し経験していくと自然と覚えていくこともたくさんあります。
そうなって来た時こそ、学びなおしをすることが大切になってきます。
5年くらい経験してくるとなんとなくできるようになってきた感覚があって、面白さもあるのですが慣れてくるといつの間にか色々な解釈に自分流も入ってきます。わかってきたと思っていたことも、改めて基準書などの原文を読んでみると、思っていたニュアンスとちょっと違っていることに気づくこともよくあります。
それはこちらの理解度が上がっていることによって本質を読み解けるようになった証拠でもあります。また、定期的に基準書を読むことで、周辺知識に対してもどこに何が書いてあるかを把握するきっかけになって、立ち戻れる場所が増えていきます。
これを繰り返していくことで、根拠がしっかりしてくるので自分も安心して設計を進められるし、周囲からの評価も変わってきます。常に根拠を明確に示せるようになると、社内外共に相手の反応が本当に変わります。
年に何度かは振り返りの時間を設けることはおススメです。時間ができたらではなく、いつやるかを明確に決めることも重要です。
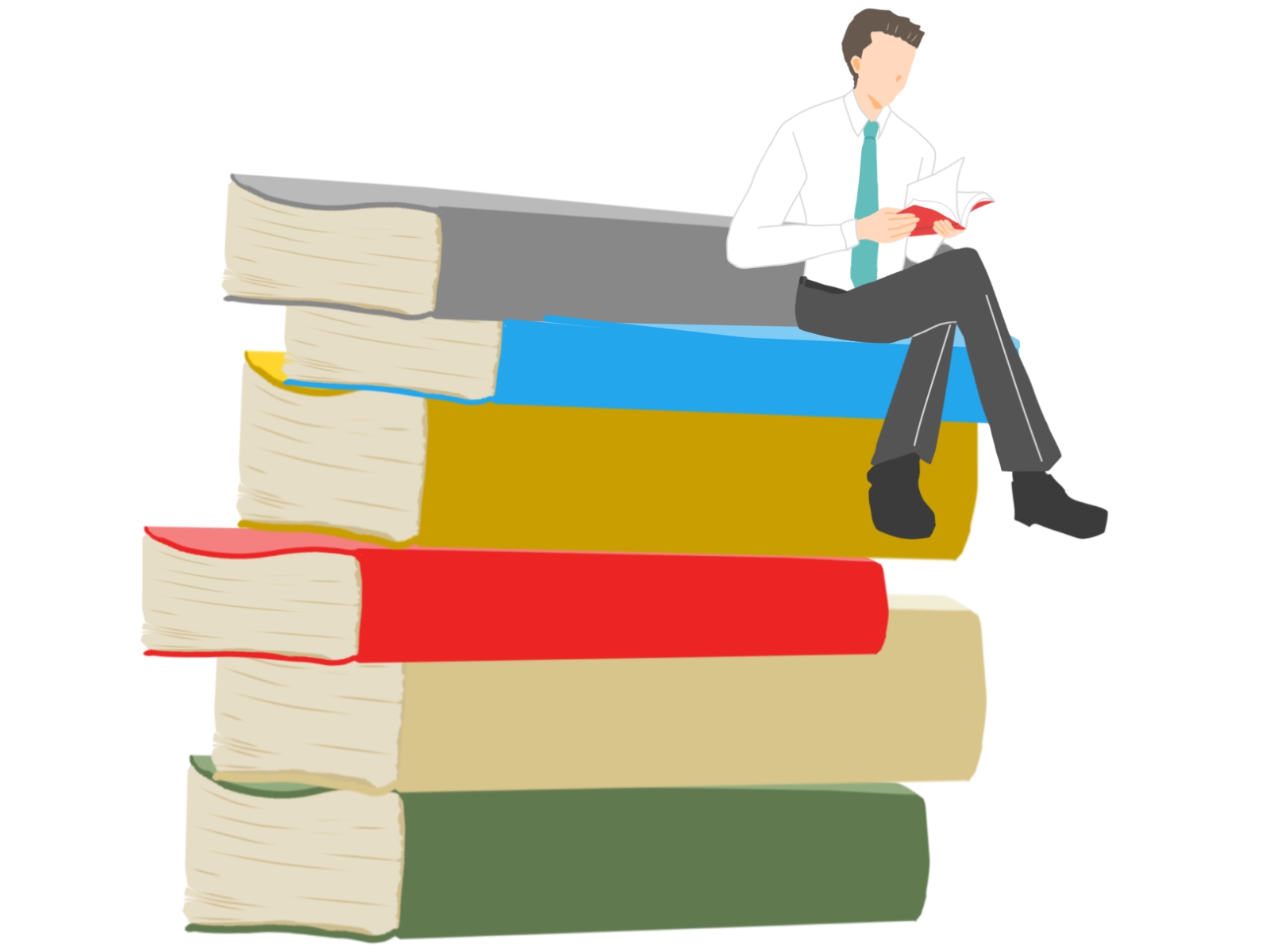


コメント