構造設計は未知の自然外圧に対しての安全性を考える必要があるため、絶対がない世界です。
人間の追求力というのは未知の課題に取り組んでいくことで成長していくものです。ゲームのレベル上げとは違って倒せる敵を何度も倒したからといって成長していくことはできません。
未知の課題というのはボスキャラのように特別な存在でなかなか遭遇しないものではなく、気付いていないだけ身近な課題の中にもたくさんあります。
構造設計に限らず工学の世界ではわかったつもりというのは最大の敵になります。
⇒構造計算プログラムに使われない付き合い方~わからないことや不整合が追求の源泉
そんな未知課題との向き合い方について書いていきたいと思います。
今回のポイントは3つになります。
①未知課題に向かっていけるようになるには?
②対象の広がりと合わせて成果レベルが変わってくる
③自分から課題に挑戦していけば活力も上がる!
①未知課題に向かっていけるようになるには?
まずはどんなときに未知課題を逃しているのかを考えてみると大きくは以下のような内容に分類できるのではないかと思います。
・仕事に慣れてきてわかっているつもり・成果が出ているという過信
・忙しくなって仕事を増やしたくないという気持ち、
・出来ないことに挑戦して失敗するのが怖い・失敗するくらいならできる定型課題の方がマシ
・対象性が狭く目の前にある課題、与えられた課題にしか目に入っていない
こういった気持ちを持って仕事をしていると成長の機会を逃すことが増えてしまいます。結果としてのすぐに成果も頭打ちします。
どんな時でも自分の成果に対しては謙虚な気持ちと無能の自覚を持つことを忘れてはなりません。構造設計においてもどんなに計算プログラムが進化しても、完璧な正解はなく常に自然に対して謙虚でいることと、未知をはらんでいることを忘れてはいけません。
また、自分が役に立っているかどうかは自分で評価するものではなく周りからの評価でしかなく、自分で役に立っていると思っていてはすぐに役に立たなくなります。
②対象の広がりと合わせて成果レベルが変わってくる
意識のあり方の次に具体的に思考部分について考えていきたいと思います。
自分の見えている範囲だけでものごとを見ていても、未知課題に対しての感度は上昇していきません。そこで有効なのは、社内外に関わらず他の人ならどういう視点、理由でどう考えるだろうか?ということを考えることです。
社会でスピード感を持って成果を出すための基本はとにかくまず真似ることです。ネットに書籍、SNSなど真似るための情報はかなり手に入れやすくなっています。
真似る際にも不可欠なことが謙虚であることです。変に自分の偏見をいれてしまうと視野を広げるための真似ではなく、結局自分の世界の中で考えていることになってしまいます。
対象性が広がっていくと、今までは気付いていなかった課題がたくさんあることを自覚することとなります。それらの課題にしっかりと向き合って追求していけば確実に成果のレベルが変わっていきます。
その結果として、自分の評価へのこだわりもなくなったり、今まで悩んでいたことも小さなことに思えてきたりと、気持ちも軽くなるし、前進感が生まれます。
実際に経験を積んで出来ることは増えていっても、わからないことも同じくらい増えていきます。
しかし、前述したような構造を理解していないと、『わからないこと=できていないこと』と誤解してしまい活力をなくしてしまうことがあります。
『なにがわからないかがわかるよう』になることはエンジニアとして必須な要素なので自信を持ちましょう。
参考:『何がわからない』かが”わからない”のはなぜ?
③自分から課題に挑戦していけば活力も上がる!
大抵の人が誰かに言われたことをするよりも、自分からやろうと思ったことをした方が意欲は高く、結果として成果のレベルも高くなります。
自分で未知課題を発見できるようになれば、自分から課題に積極的に取り組んでいくことができます。今までよりも苦労する部分も増えるかもしれませんが、結果的には充実感も高くなります。
みんなの役に立つための力が付いていることや、新しいことを知れたということを素直に喜べればより楽しくなると思います。
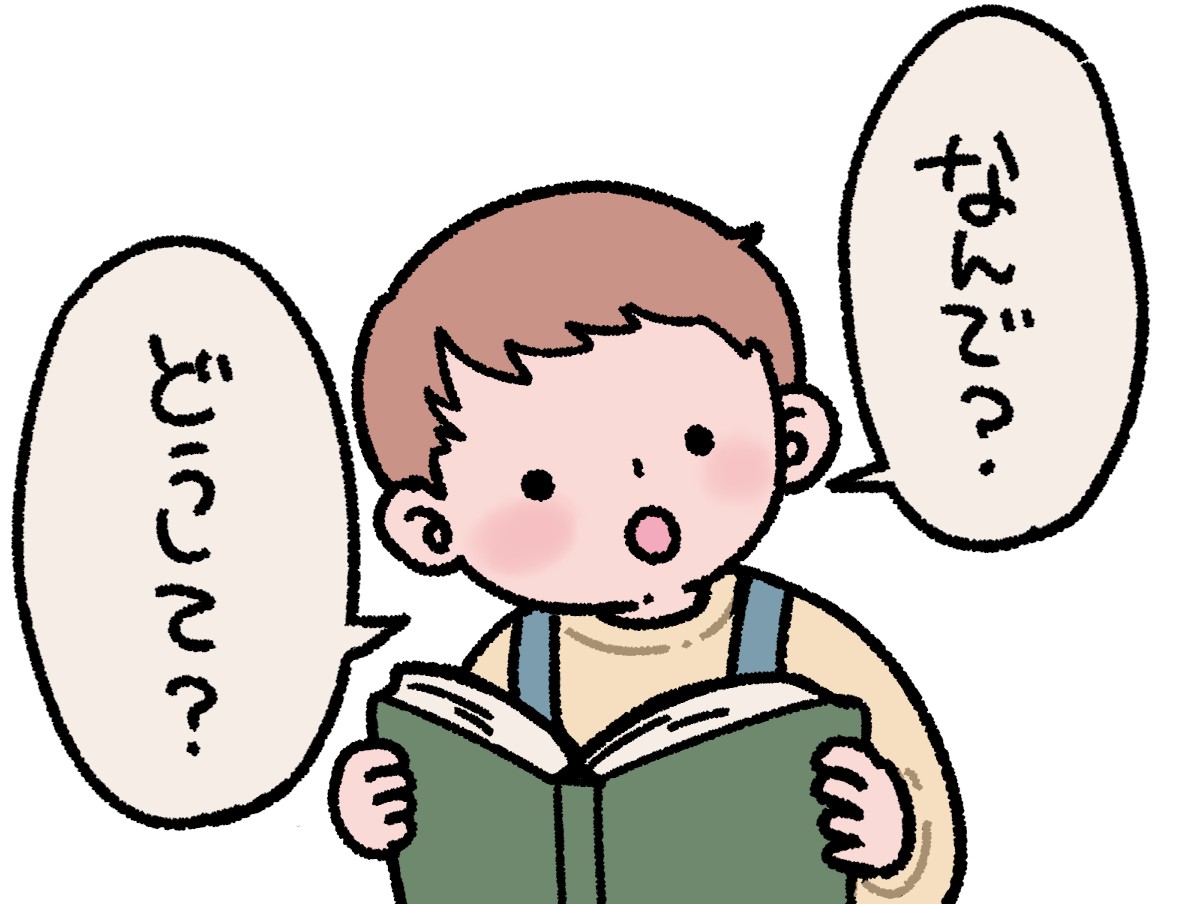


コメント