これまでの記事ではあまり方法論的なところに焦点をあてないものにしてきました。
構造設計に限りませんが、方法論をなまじで身に着けてしまうと、深く考えずに課題を処理する方向に思考が向かってしまうことへの懸念があると思います。、
そうではなく本質を知って設計する面白さを知ってもらえることに繋がることを中心に記事にしてきました。
一方で、設計者として一級建築士の試験は、かなりの時間と精神力を使って取得するものになっています。そこで努力することの大切さや幅広い知識を身に着けることは重要なことではありますが、1回で合格するに勝ることはありません。
自身が1級建築士の試験を受けたのは10年以上前になってしまいますが、その後も学科の構造部分に限りますが、継続的に身近な人たちにレクチャーを続けていく中で役に立ったと思わる認識を記事にしていきたいと思います。
今回の内容だけを覚えるというよりも、これらの内容を知っておくことで勉強時間の短縮や暗記量を減らすことで、構造の勉強時間の効率化により、暗記科目の時間が取れて全体的な点数の向上に繋げてもらえればと思います。
今回のポイントは3つになります。
①試験問題の体系を理解する
②言葉の表現に注目する
③言葉の定義を正確におさえて分類
①試験問題の体系を理解する
国家資格の試験問題ということもあり、見方によって適合か不適合化の判断が変わるものは選択肢に入れることはできません。絶対的な判断ができないものは問題にできないです。そんなものが問題が入っていたら後々クレームになる可能性もあります。
法で定められていたり基準書で絶対的に言い切っていないものについては、状況判断ができてしまうので絶対に不適合と言い切ることができなくなります。
試験では選択肢があるので完璧な判断をするのではなく明らかに危険側の判断になっていないかを見抜くことができれば判断することができます。
なのでまずは大きな概念を理解すればよくなります。その際にもどういったものが危険側に振れる可能性があるのかを意識すると、インプットの仕方も変わってくると思います。
②言葉の表現に注目する
上記を踏まえると極端・あいまいな表現については以下のように考えることができます。絶対に以下のような言葉が出てきたら適切・不適切のどちらかとは言えませんが、大きな傾向として認識しておくと役に立つとは思います。
極端・あいまいな表現の例
・〇〇により検討を不要とした。
不要と言い方をしてしまうと、まったく確認をしなくてもよいということになってしまいますが、おおよそ問題ないと思えることでもまったく確認なしに問題ないとは言い切れない。
・適切な〇〇
非常に幅がある言葉であって、不適切なことをすることはないので、適切に〇〇したと言われたら不適切と言うことはできない。
・〇〇に効果がある
どの程度の効果があるかが具体的に示されていない場合には、よほどの検討違いのことを言わない限りは効果がまったくないとは言い切れません。
・〇〇しなければいけない
これも絶対的な縛りとなってしまい設計者思想や設計条件の余地がないことになってしまうので、この表現が入っている場合は不適切になる。
③言葉の定義を正確におさえて分類
大きな概念理解をするにあたっては、言葉については1つ1つの定義を正確におさえる必要があります。言葉についても概念理解にしてしまうと、概念理解に概念理解を重ねることになり、知識が体系化できなくなってしまいます。結果として1対1で暗記をすることになり、暗記量が膨大になってしまいます。
軸となる言葉は意外と少ないのでどれのカテゴリーに該当しているのかを分類しながら読み取ると、まったく新しいことが少なくなり色々な知識を繋げて覚えられます。
体系化する際に以下の内容について正確に分類しておくだけで理解はしやすくなると思います。
・時間軸 長期(使用性)、短期(損傷)、終局(安全性)
・外力の種類 曲げ、せん断、軸力
・外力と耐力を区別する
・剛性と耐力の違い
・公式の乗数、単位(何が影響が大きいのか)
・一次設計(弾性設計・中地震)⇒とにかく壊れないように設計する、耐力も上げれば安全側
・二次設計(塑性設計・大地震)⇒壊れ方を設計する
せん断破壊・座屈のような危険は壊れ方に繋がる耐力の上げ方はしない
単に耐力を上げれば全部が安全側とはならない
剛性のバランス(偏心率、剛性率)をとることは必須
こちらの記事も一級建築士向けに書いているのでぜひ参考にしてください。
参考:建築構造設計の世界を知る~自然の未知をどう掴むか
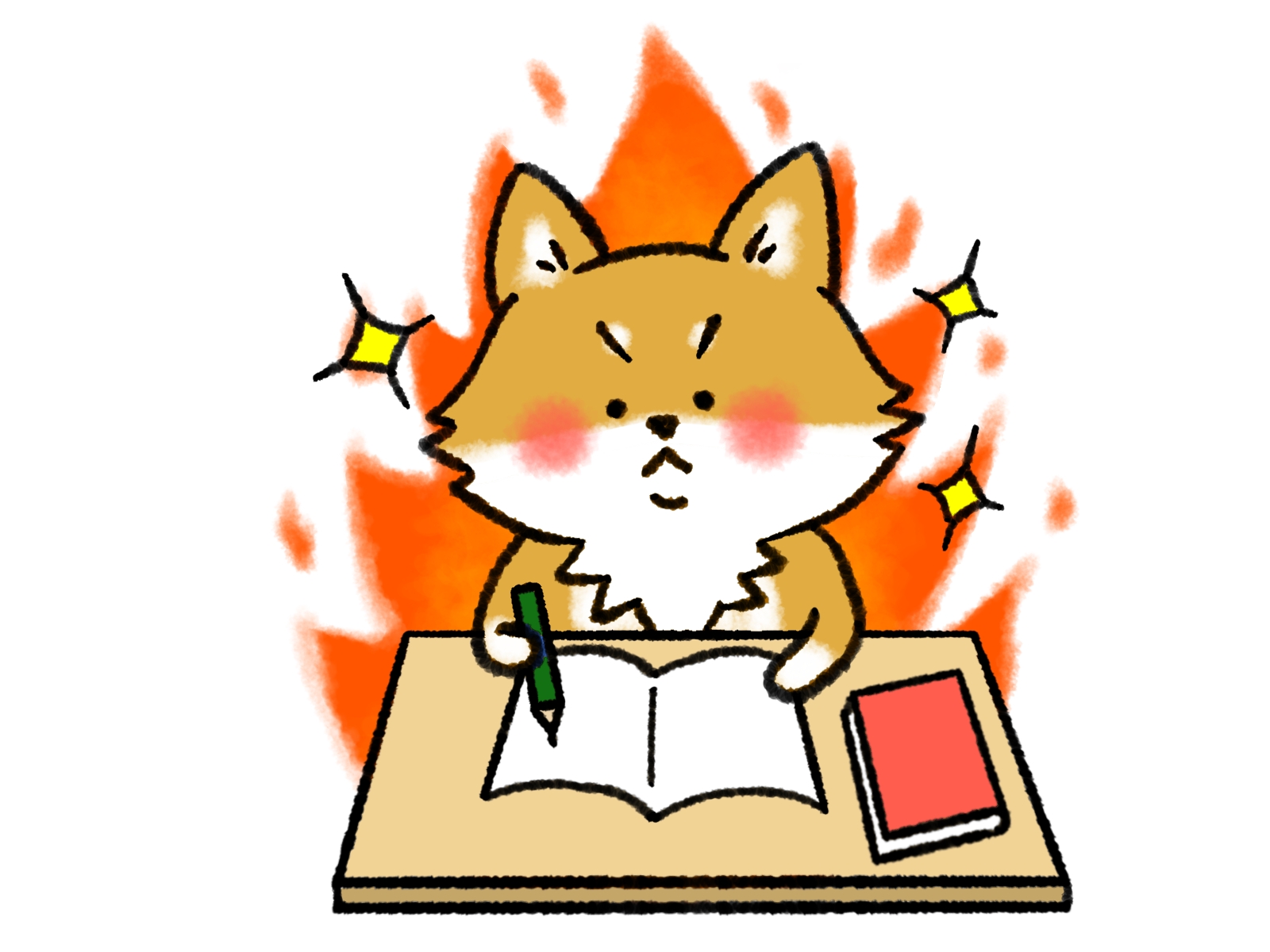


コメント