設計を進める中で構造図以外の図面もチェックすることで部門間調整をしてくことになりますが、その際にある程度の理解がないと大量の情報の中で何を見てよいかわからないことになってしまうと思います。
調整せずに進んでしまうと設計終盤での手戻りや現場での設計変更が発生してしまうことになります。
図面のチェックの視点という形で書きますが、チェックの内容を理解できるようになれば、計画や基本設計段階でも全体を見通した構造設計もできるようになっていきます。
他部門のことを理解できるようになってくると提案の幅も広がってくるので構造設計もより楽しくなっていくと思います。
今回は設備図の中でも機械設備に絞って書いていきます。
〇システムの把握
機械設備図では大きく分けて空調・換気・衛生があります。(発注者によってはエレベータが入ることがありますが、主体的な内容ではないので今回は割愛します。)
空調と換気であれば大きくは個別空調なのか中央空調なのかで構造への影響が大きく変わってきます
衛生関連については、給水の引き込み方式によってポンプや水槽の有無が変わってきます。
まずは大きなシステムを把握することで何が登場するのかをおさえましょう。
〇シャフトスペース
主にPS(パイプスペース)やDS(ダクトスペース)が機械設備で使用するシャフトスペースになります。言葉の通りですがPSには上下階を結ぶ主配管、DSは上下階を結ぶ主ダクトが通っています。
配管の詳細としては、空調用の冷媒管やドレン配管、給水管、排水管などになります。これはほとんどの建物に出てくる内容になります。
一方でダクトは空調・換気システムによってスペースが大きく変わってきます。中央空調システムを採用している場合には機械室から各所に新鮮空気を運ぶので大きなダクトがDSに限らず、各階の天井裏などを走っていくことになります。中央空調システムの場合には、空調と換気を兼ねます。
中央空調システムを採用していない場合でも、厨房のように火器設備を集中的に使用する部屋がある場合にはその周辺に多くのダクトが出てきます。換気を多く必要とする場所はおさえておきましょう。
PSについてはしっかりとした室で取らずに柱に抱かせる場合がよくあります。その場合には柱に取りつく梁幅によって確保できるスペースが決まってきます。断面の変更でスペースをつぶさないように気を付けましょう。縦に通っていくので一部の階で梁幅を変えてしまうと配管が通らないことになります。ピットまでいく場合には基礎梁やフーチングとの干渉にも気を付ける必要があります。
大きく床に開口を設ける場合には適切に床を支持する梁を追加したり、耐震要素に近い場合には水平力の伝達が問題ないかの確認を忘れないようにしましょう。
〇ダクトルート
ダクトは配管と比べてサイズが大きいので、あらゆるスペース調整の中で最も影響が出てきます。このダクトの通し方によって部材サイズが決まることがあります。
まず大きくは梁下を通すのか、梁貫通スリーブで通すのかに分かれます。
梁下に通すのであれば階高を上げる、梁せいを小さくする、もしくは梁をなくすなどの調整が出てきます。梁貫通スリーブで通すのであれば、梁サイズによって最大スリーブサイズが決まってきます。スリーブ径を大きくするためにあえて梁せいを大きくすることもあります。
ダクトは主に換気で使用されますが、給気と排気がそれぞれどのようなシステムで完結してるのかを把握して、それの通り道を踏まえて断面計画を提示することを意識しましょう。
ダクトサイズを小さくしたいときには、系統を分岐する(本数は増えるが小さくなる)、部分的に扁平させる、外壁から直接接続するなど、いくつか方法はあるのでお互いに歩み寄って上手く調整しましょう。
〇配管ルート
設備の配管は冷媒管、給水管といった圧力で送れる配管は径も小さく、勾配もないので割と調整がしやすい(自由が利きやすい)ものです。
一方で排水管、ドレン配管といった自然の力で水を流すものについては勾配が必要となるので、スリーブで通そうと思うと梁によって貫通する位置が異なってくるため注意しましょう。
場所によっては思ったより配管が下がって来ていて梁主筋と干渉する位置になっているということもあります。
配管においては種類を把握しながら調整するようにしましょう。
〇天井の機器
天井には空調機や換気設備(全熱交換器など)が大きなものが取りつきます。その際には梁下に十分おさまっているか、もしくは梁の間に設置するのであればその意図にあった梁の掛け方になっているのかを確認しましょう。
〇はと小屋
はと小屋については荷重に影響してきます。屋外の設備機器とシャフトスペースを接続するためには必ずはと小屋が出てくるので、シャフトの接続の仕方とセットでおさえておきましょう。どの高さでどのような大きなのものが通るのかを踏まえて躯体形状も決めていきます。
はと小屋自体が大きい場合にはどのように自立させるのかもしっかりと検討して必要に応じて受け梁などを配置するようにしましょう。
〇機器荷重
設備機器荷重自体は図面には書いていませんが、確実に伝達してもらって構造設計に反映しましょう。自分が把握している内容と図面に齟齬がないかは都度図面で確認するようにしましょう。
機器の荷重だけでなく、コンクリート基礎の上に機器を設置することもあるので、基礎の情報についても図面で確認するようにしましょう。コンクリートは比重が大きいので抜けると構造計算への影響も大きいので早めに機器の設置の仕方については調整しましょう。
また、竣工時に設置されているものだけでなく、将来の更新や増設も見通しての荷重設定も重要なので建築計画と合わせて適度に設定しましょう。
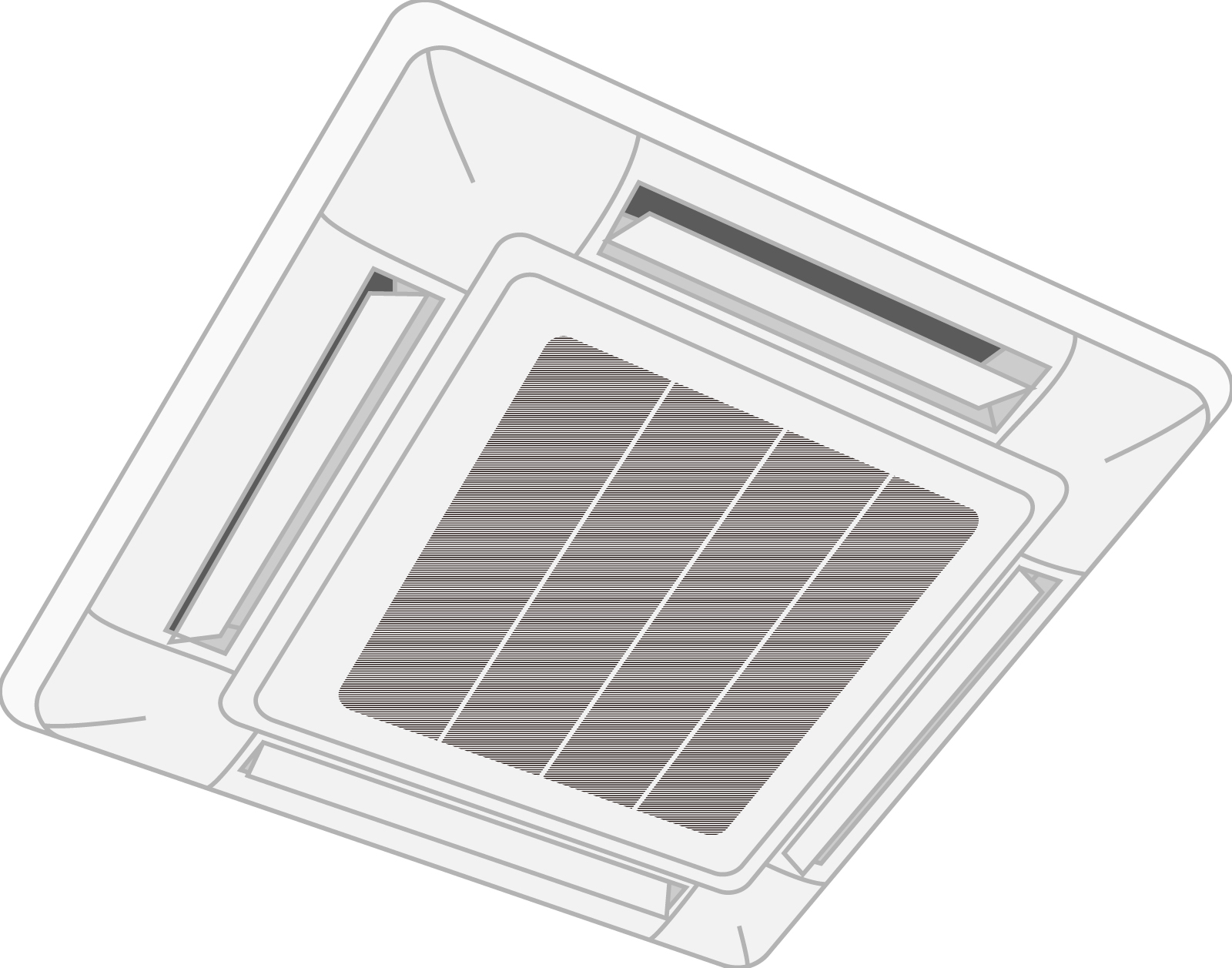


コメント