 【構造設計】
【構造設計】 【構造設計】杭の耐震設計の水平力
【構造設計】杭の耐震設計の変遷と今後考えたいことこちらの記事の続編になります。地震時の水平力に対する検討について焦点を当てていきます。基礎に作用する地震荷重を静的に評価する場合は、これを上部構造の地上部分及び地下部分の重心位置に作用する慣性...
 【構造設計】
【構造設計】  【一級建築士】
【一級建築士】  【構造設計】
【構造設計】 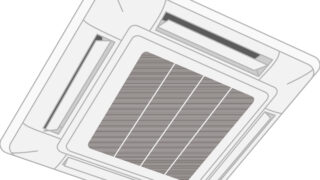 【構造設計】
【構造設計】  【一級建築士】
【一級建築士】  【構造設計】
【構造設計】 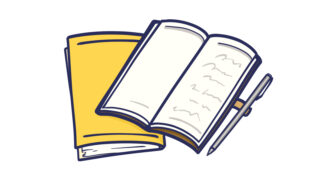 【人材育成・仕事基礎】
【人材育成・仕事基礎】  【構造設計】
【構造設計】  【構造設計】
【構造設計】  【構造設計】
【構造設計】